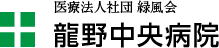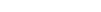リハビリテーション部
特徴

従来の脳血管疾患、運動器疾患、呼吸器疾患に加え、がん疾患、心大血管疾患を対象に行っており、リハビリテーションの専門性を強化しています。また、糖尿病患者様への運動指導も行っています(糖尿病教育入院)。
理学療法士23名、作業療法士4名、言語聴覚士5名で治療を提供しています。
資格取得
「がんのリハビリテーション研修会」修了者:12名
(医師2名、看護師2名、理学療法士5名、作業療法士2名、言語聴覚士1名)
糖尿病療養指導士:1名
心臓リハビリテーション指導士:1名
心臓リハビリテーション学会員:3名
地域包括ケア推進リーダー:1名
介護予防推進リーダー:1名
対象疾患
脳血管疾患
脳卒中、パーキンソン病、脊髄小脳変性症等
運動器疾患
骨折、関節症、リウマチ、腰痛症等
呼吸器疾患
肺炎、喘息、慢性閉塞性肺疾患等
心疾患・大血管疾患
心筋梗塞、狭心症等、慢性心不全、心臓バイパス術後、心臓弁置換術後等
がん疾患
がんリハビリテーションチーム

その人らしい生活を過ごせるように支援していきます。
がんリハビリテーションは、研修を修了した、医師、看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士で構成されています。
がんリハビリテーションの目的は、がん患者のADL(日常生活動作)・基本動作の安全性の確立、能力向上、疼痛緩和による在宅復帰を目指すことです。
当院では、維持期~緩和期の患者さんが主となります。
内容は、患者さんの状態によって決定・変更していきます。
患者さん自身と家族の希望に寄り添ったリハビリテーションを提供できるよう、リハビリテーションスタッフだけでなく、医師、看護師、ケアマネージャーなどの専門職と意見交換や情報提供をしながら治療をすすめていきます。
維持的リハビリテーションは、運動能力の維持や回復を図るために行います。
自助具の使用を視野に入れて、その操作のコツやセルフケアの習得を行います。
機能の低下している動作を維持するための軽い運動や、動作をサポートする道具の使い方などを習得します。
さらに進行するかもしれない筋力低下に対するアプローチも行います。
緩和リハビリテーションとはQOL(生活の質)を優先させる段階で行うものです。
苦痛の少ない姿勢の習得、または家族に指導したり、スキンケアの方法の習得、体力を維持し、負担を軽減するための方法を習得します。
また、痛みに対しては薬を併用しながらマッサージやポジショニングを行い、苦痛を伴わない、その人らしい生活を過ごせるように支援していきます。
心臓リハビリテーションチーム




突然死や再発のリスクを軽減することを目指しています。
心臓リハビリテーションは、循環器内科医、理学療法士3名、作業療法士1名(心臓リハビリテーション学会員3名)で構成されています。
心臓リハビリテーションの目的は、心疾患に基づく身体的影響を軽減し、突然死や再発のリスクを軽減することを目指しています。
心臓リハビリでは、毎回患者さんの血圧や体調等のバイタルチェック、準備運動、心電図でのモニタリングをしながらの自転車エルゴメーター、レジスタンス運動(筋トレ)、整理体操、再度バイタルチェックを行っていきます。
同じ境遇の方と一緒に運動することで情報の交換も行われています。
モニター心電図、自転車エルゴメーター、運動負荷試験装置、自動血圧計等、各種機器が揃っています。
施設基準
- 脳血管リハビリテーションⅠ
- 運動器リハビリテーションⅠ
- 呼吸器リハビリテーションⅠ
- 心大血管リハビリテーションⅠ
- がん患者リハビリテーション
主なスタッフ紹介
- 役職
- リハビリテーション部 部長
- 専門分野・資格
- 理学療法士
専門理学療法士(運動器)
- コメント
- 医療・介護保険制度の見直しによりリハビリテーション医療の需要が飛躍的に高まっています。そのような状況の中、療法士の世界は個々の質を問われる時代に入っています。すなわち臨床現場においては臨床技術に加え、コンプライアンス、コミュニケーション能力、リーダーシップや自己啓発に至る能力が要求されます。当院では教育システムを構築し、このガイドラインを使用する事で自らの課題を見出し、専門職として質の高いリハビリテーション医療を提供得きるよう日々研鑽していただきたいと思います。

- 役職
- リハビリテーション部 課長
- 専門分野・資格
- 理学療法士
心臓リハビリテーション指導士
認定理学療法士(代謝・循環)
糖尿病療養指導士
- コメント
-
当院のリハビリテーション部は「がんリハビリテーション」「心大血管リハビリテーション」を実施している希少な病院です。専門資格を有している職員も多数在籍しており、より専門的な介入を行っています。
また、リハビリテーション室は明るく、楽しい雰囲気な為、実際に治療されている患者さんもとても良い表情で頑張っておられます。退院後を見据えた支援も行っていますので、当院で治療して在宅復帰を目指しましょう。

求人に関するご質問
Q1.見学の依頼をしたいのですが、どうすればよいですか?
ホームページの求人情報⇒病院見学⇒入力フォームに必要事項明記して頂ければ幸いです。
Q2.教育体制はどのようになっていますか?
当院のリハビリテーション部では独自の教育システムを運用しています。新卒者や経験の浅い方にはプリセプターがつきます。入職後約2週間は院内のローカルルールや、診療報酬のことなど専門資格がなくても出来る仕事の内容を覚えていきます。3~4週目には実際に患者さんの評価や治療の一部に関わりながら技術や知識の確認をしながら業務に慣れていきます。5週目以降は少人数から実際に患者さんを担当していきます。担当開始後も先輩セラピストが近くで見守りながら実施するため安心して治療を提供することができます。
おおよそのスケジュールは設定してありますが、柔軟な対応は必要な場合もありますので随時相談して頂ければと思います。
また、院外への勉強会参加のバックアップ体制も整っていますので、自身のスキルアップも望める環境となっています。
Q3.働いているスタッフの年齢層は高いですか?
病棟、外来、訪問リハビリで10年目以上は6名です。経験も豊富なので相談にも乗ってもらえると思います。年齢層は20代が多く、元気のある若いセラピスト達が盛り上げてくれています。
Q4.怖い上司はいますか?
我々リハビリ専門職は患者さんに対して一定の負荷をかけながら治療していく職種であるため、その方法に誤りがあれば重大な事故に発展しかねません。そうならないために、必要なときにはしっかりと叱ってくれますが、普段は冗談を言ったり笑い話が好きな方々です。
Q5.働きやすい職場ですか?
働きやすさの基準は人それぞれですが、それでも働きやすい環境だと思います。
若いセラピストが多いこともあり、アットホームな雰囲気のリハビリ室です。
休日も前もって伝えておけば希望通りに休むことが出来ますし、体調不良等の急な休みの際にも「みんなでバックアップをするから大丈夫!」という雰囲気ですので、安心して休むことができます。
Q6.勉強会は絶対に参加しなければなりませんか?
勉強会は強制ではありません。ただ、この仕事は生涯にわたって自己研鑽が必要だと思います。院内勉強会、外部の勉強会、自身で買った参考書や院内図書を利用した勉強の仕方は様々です。
Q7.休日の希望は受け付けてもらえますか?
当院は希望の日に休むことが出来ます。仮に他にも多くの方が同日に休日希望を出す場合は患者さんのご迷惑になってしまいますので相談させてもらう場合があります。前もって休みたい日が決まっている(旅行等)場合は、皆で協力しながら臨機応変に対応していきたいと思います。
Q8.残業はありますか?
定時の17時半に業務が終えられるように意識しながら業務組んでいます。急な会議や入退院によって若干の残業が生じることもあります。
※17時半以降で院内勉強会を行うことはありますが、こちらは強制ではありません。業務ではなく自己研鑽の時間となります。
Q9.患者層を教えてください。
当院は一般病棟と療養病棟のケア・ミックス病院です。年代は高齢の方がほとんどを占めます。疾患別リハでは、運動器疾患(骨折術後、圧迫骨折)、内科疾患(糖尿病、心不全、肺炎)が多く、脳血管疾患やがん疾患も一部入院されています。運動器疾患は術後の回復期の方が多く、内科疾患は急性期の方が多いです。脳血管疾患は生活期の方がほとんどですが、一部回復期の方も入院されています。
Q10.望まれる人物像があれば教えてください。
医療というのはチームで動くことで良い結果を出すことが出来ます。そのため協調性があり、コミュニケーションがしっかり出来ることが必要です。
そして、リハビリ職は治療による結果が求められる職種でもあります。そのためにしっかりと自己研鑽に励むことが望ましいと考えています。